理学療法士と作業療法士。
この2つはリハビリ関連の中でも、特に混同されやすい職種です。
そこで今日は様々な観点から、理学療法士と作業療法士の違いについてみていきましょう。
法律上の違い
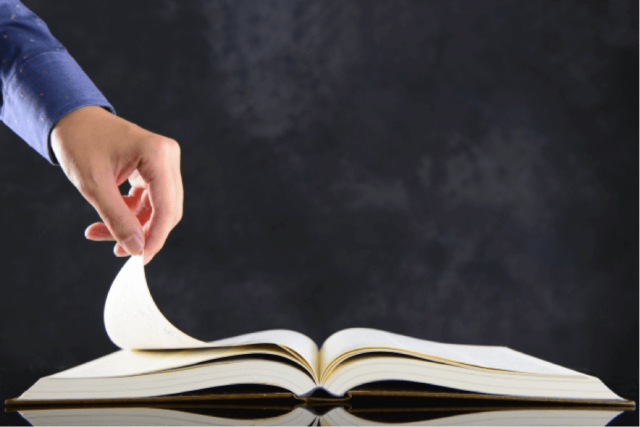
まずは、理学療法士と作業療法士の定義について見ていきましょう。
それぞれ、昭和40年に制定された以下の法律で定められています。
ここに、明確な違いが記載されています。
理学療法士及び作業療法士法
理学療法とは
「身体に障害のある者に対し、主としてその 基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺 激、マツサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう」
作業療法とは
「身体又は精神に障害のある者に対し、主として その応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行なわせることをいう」
では、この法律から読み取れる理学療法士と作業療法士の違いについて、もう少し詳しく解説していきます。
対象者の違い

理学療法の対象者は、身体に障害のある方です。
具体的には、以下のような疾患が中心となります。
中枢神経疾患
脳卒中、脊髄損傷、脳の外傷、中枢神経の変性疾患、腫瘍、脳血管の異常、脳炎、小児発達障害など
整形外科疾患(運動器の障害)
手足、脊椎の骨折、腰痛、頸部痛、肩関節周囲炎、退行変性疾患、腰椎椎間板ヘルニア、靭帯損傷、変形性関節症、四肢の切断、様々な運動器由来の疼痛など
呼吸器疾患
慢性閉塞性肺疾患、肺炎、結核後遺症、喘息、全身麻酔術後の肺機能低下など
心疾患
心筋梗塞、狭心症など
内科的疾患、体力低下
糖尿病、高齢、術後体力低下、近い将来運動機能の低下により要介助状態になることが予想される高齢者、メタボリックシンドロームによる運動指導対象者など
一方、作業療法は、上述のような身体に障害のある方に加えて、精神に障害のある方も対象となります。
具体的には、以下のような疾患が中心となります。
- 統合失調症
- 気分障害(うつ病、躁うつ病)
- 神経症
- アルコール依存症
- 発達障害
- 認知症
目的の違い

理学療法の目的は、基本的動作能力の獲得です。
基本的動作能力とは、以下のようなものを示します。
- 起きる
- 座る
- 立つ
- 歩く
一方、作業療法の目的は応用的動作能力の獲得です。
応用的動作能力とは、以下のようなものを示します。
つまり、その行為自体に目的がある動作です。
- 食事
- 整容
- 入浴
- 排泄
- 更衣
- 家事
また、作業療法では、社会的適応能力の獲得も図ります。
社会的適応能力とは、以下のようなものを示します。
- 地域活動への参加
- 就学
- 就労
以上は、理学療法士及び作業療法士法から読み取れる違いです。
ここからは、少し異なる観点から、理学療法と作業療法違いについてみてみましょう。
働く場所の違い

上述のように、理学療法士と作業療法士では、対象者や目的が異なります。そのため、働く場所においても違いがあります。
共通
- 医療施設(大学病院、総合病院など)
- 福祉施設(デイサービス、老健など)
理学療法士
- スポーツ関連施設(トレーニングジムなど)
作業療法士
- 精神科病院
- 認知症関連施設
組織の違い

理学療法士や作業療法士になると、多くの方が日本理学療法士協会又は日本作業療法士協会に加入します。
日本理学療法士協会は公益社団法人、日本作業療法士協会は一般社団法人と位置づけられています。
公益社団法人とは「公益事業を主に目的としている法人」です。公益事業とは「公衆の日常生活に欠くことのできない事業」のこと。公益社団法人を設立するにはまず「一般社団法人」として会社を設立していることが条件となります。そして、国や都道府県に対して「公益認定申請」を行ない、受理されないと設立できないのが公益社団法人です。厳しい審査のもとで設立されるので、社会的に信頼性が高い法人として扱われ、法人税が非課税になるなど、税金面で優遇されます。
一方の一般社団法人とは、ある目的をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき設立された非営利法人のこと。事業の内容について制限がなく、法務局への登記だけで設立できます。
一般社団法人も企業と同じように収益事業を営むことができますが、非営利法人のため、事業の利益は法人の活動のために使われます。
つまり、日本理学療法士協会は非営利性と公益性を国から認められており、日本作業療法士協会は非営利性のみを認められた団体といえます。
最後に
いかがでしょうか?
こうしてみると、似ているようで異なる点も多いことがわかります。
より詳しい情報が知りたい方は、それぞれの協会HPをぜひ参考にしてみて下さい。

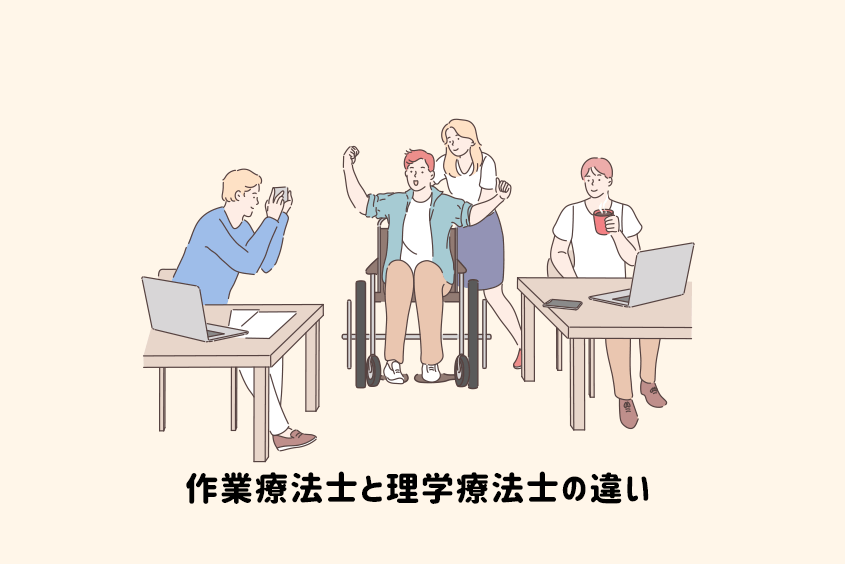
コメント